搜尋結果
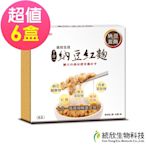 $6182$7359統欣生技 納豆紅麴禮盒(60粒/4瓶/盒)x六盒購物中心折價券
$6182$7359統欣生技 納豆紅麴禮盒(60粒/4瓶/盒)x六盒購物中心折價券 $945$1049【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X3瓶)購物中心折價券
$945$1049【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X3瓶)購物中心折價券 $1400$1666統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x2盒購物中心折價券
$1400$1666統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x2盒購物中心折價券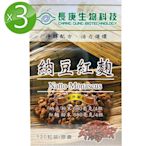 $3932$4680長庚生技 納豆紅麴升級配方3瓶組(120粒膠囊/瓶)購物中心折價券
$3932$4680長庚生技 納豆紅麴升級配方3瓶組(120粒膠囊/瓶)購物中心折價券![統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x1盒 統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x1盒]() $496$590統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x1盒購物中心折價券
$496$590統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x1盒購物中心折價券![【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X1瓶)-快 【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X1瓶)-快]() $360$399【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X1瓶)-快購物中心折價券
$360$399【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X1瓶)-快購物中心折價券![統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x6入 統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x6入]() $1664$1980統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x6入購物中心折價券
$1664$1980統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x6入購物中心折價券![統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x1盒 統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x1盒]() $748$890統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x1盒購物中心折價券
$748$890統欣生技-TX 順效納豆紅麴 30 粒x1盒購物中心折價券![多立康 活益清納豆紅麴養生植物膠囊(60粒/盒x3入組) 多立康 活益清納豆紅麴養生植物膠囊(60粒/盒x3入組)]() $1304$1650多立康 活益清納豆紅麴養生植物膠囊(60粒/盒x3入組)購物中心折價券
$1304$1650多立康 活益清納豆紅麴養生植物膠囊(60粒/盒x3入組)購物中心折價券![統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x2盒 統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x2盒]() $790$940統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x2盒購物中心折價券
$790$940統欣生技 納豆紅麴60粒/盒x2盒購物中心折價券![【生寶國際生技】頂級納豆紅麴加強版膠囊1入組(共90粒 添加銀杏/輔酵素Q10) 【生寶國際生技】頂級納豆紅麴加強版膠囊1入組(共90粒 添加銀杏/輔酵素Q10)]() $999【生寶國際生技】頂級納豆紅麴加強版膠囊1入組(共90粒 添加銀杏/輔酵素Q10)購物中心折價券
$999【生寶國際生技】頂級納豆紅麴加強版膠囊1入組(共90粒 添加銀杏/輔酵素Q10)購物中心折價券![【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X6瓶) 【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X6瓶)]() $1710$1899【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X6瓶)購物中心折價券
$1710$1899【得意人生】高單位納豆紅麴膠囊 (60粒X6瓶)購物中心折價券
概要. 大豆を 納豆菌 で 細菌 発酵(「 臭気 」を参照)させた 発酵食品 で、多数の 栄養素 をバランス良く含む 健康食品 でもある。 和食 の基本的な食材の1つとして、日本全国の食品売り場で1年を通して安価(65 - 100円程度 [5] )・容易に入手できる。 低コストでありながら高い健康効果が得られるが、特有の癖があるため、人により好き嫌いは分かれる。 高い健康効果があるとは言え、1日当たりの摂取量は1パック(40 - 50g程度 [6] )が適量であるため、食べ過ぎには注意が必要である [7] 。 食べ過ぎた場合、 婦人科疾患 や 痛風 などで健康を損なう場合がある [8] 。 「納豆」「 納豆汁 」などは冬の 季語 である [注釈 1] 。
概要. インターネット上でも納豆PRセンターを通して納豆の調理法や、納豆の健康効果等、納豆に関する様々な情報を広く提供する事業を行っている。 一時期は所属企業が300社を超えた事もあったが 2006年 (平成18年)の深刻な 原油価格 高騰にともない多くの業者が廃業し現在は300社を割り込んでいる。 納豆の日本一を決定する全国納豆鑑評会を主催している事でも有名である。 歴史. 1939年 ( 昭和 14年) - この頃より各県で納豆組合ができ始める。 1941年 (昭和16年) - それらの納豆組合が集まって全国納豆工業組合協会を設立する。 1954年 (昭和29年) 4月 - 中小企業等協同組合法 に基づいて各協同組合からなる協同組合連合会とし、同時に全国納豆協同組合連合会と改称する。
納豆菌 (なっとうきん、学名: Bacillus subtilis var. natto )は、 枯草菌 の一種である。 稲 の 藁 に多く生息し、日本産の稲の藁1本に、ほぼ1000万個の納豆菌が 芽胞 の状態で付着している [1] 。 研究. 納豆菌の発見. 最初に日本化学会誌に納豆菌に関する論文を発表したのは、1894年(明治27年)から3年間にわたり 農科大学 の大学院生だった 矢部規矩治 である [2] 。 矢部は、 納豆 発酵中の化学変化について研究を続け、桿菌1種と球菌3種を発見したが、納豆の粘着物質である糸の生成原因に関しては研究未完に終わり、納豆菌の発見までには至っていなかった [3] 。
大徳寺納豆 (だいとくじなっとう)は、 京都市 北区 紫野の 大徳寺 門前で生産されている 納豆 である。 寺納豆 の一種。 概要. 大徳寺納豆は現代一般的に呼ばれる 納豆菌 を発酵させて作った粘り気のある糸を引くような 納豆 とはまったく異なり、塩味の強い古来の製法に則って製造された食品である。 酒肴やお茶請けとして用いられる他、寺では粥において塩の代わりに使われるほか、原型となった豆豉のように料理の調味料としても用いることができる。 京都 では、大徳寺納豆を用いた 京菓子 が各種存在する。 大徳寺納豆は、納豆菌ではなく 麹菌 を使用して発酵させ、乾燥後に熟成させたものである。 風味は 味噌 や 醤 、中国原産の 豆豉 に近い。 大徳寺 ではこの食品を 一休宗純 が伝えたものとしている。
天狗納豆 (てんぐなっとう)とは、 水戸納豆 の 発祥のブランド 名。 複数の企業がこのブランド名で 納豆 を製造している。 歴史. 水戸納豆の歴史. 「天狗納豆総本家」を名乗る笹沼五郎商店. 笹沼五郎商店の納豆展示館. 江戸時代 末期の 安政 元年(1855年)、 水戸藩 士で勤王家の笹沼家に初代笹沼清左衛門が生まれた。 初代笹沼清左衛門は1889年(明治22年)に天狗納豆を興し、今日の 水戸納豆 の礎を築いた。 天狗納豆の由来. 水戸徳川家家臣郷士庄屋神官層が主軸となり、8代水戸藩主 徳川斉昭 に重用された「藩政改革・尊皇攘夷派」に属した。
概要. 主な材料は、 小豆 、 ささげ (大角豆)、 えんどう豆 、 そら豆 、 いんげん豆 、 紅花いんげん (花豆)。 落花生 や 大豆 (主に 黒大豆 : 黒豆 )なども用いられる。 これらを 砂糖 と共に甘く煮詰め、さらに 砂糖 をまぶしてから 乾燥 させて作る [2] 。 由来には諸説有る。 関西 に弟子の多い岡女堂では、 安政 年間に甘納豆の老舗である岡女堂 [3] の初代である大谷彦平が京都 本能寺 門前にて ぜんざい を火にかけすぎたことから偶然に甘納豆を発見し、 大徳寺納豆 から甘納豆と名付けた。 そして1895年( 明治 28年)の第4回 内国勧業博覧会 の京都開催時に「ぼうだいの甘納豆」として出品され、 宮内省 御用達 となったとされている。
麹 、 糀 (こうじ)は、 米 ・ 麦 ・ 大豆 などの 穀物 に コウジカビ などの食品 発酵 に有効な カビ を中心にした 微生物 を繁殖させたものである。 コウジカビ は、増殖するために 菌糸 の先端から デンプン や タンパク質 などを分解する様々な 酵素 を生産・放出し、培地である蒸米や蒸麦のデンプンやタンパク質を分解し、生成する グルコース や アミノ酸 を栄養源として増殖する。 コウジカビの産生した各種分解酵素の作用を利用して 日本酒 ・ 味噌 ・ 食酢 ・ 漬物 ・ 醤油 ・ 焼酎 ・ 泡盛 など、 発酵食品 を製造する時に用いる [1] [信頼性要検証] 。 ヒマラヤ地域 と 東南アジア を含めた 東アジア 圏特有の発酵技術である。









