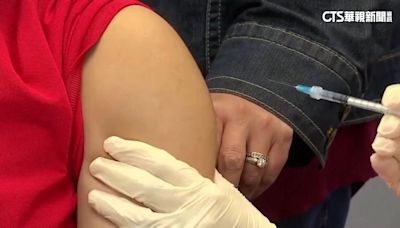搜尋結果
日本 における 自殺 (にほんにおけるじさつ)は、厚生労働省が公開している人口動態統計の死亡者総数に対する死亡原因別のシェアとランキングでは、2017年度は1位は癌で27.9%、2位は心疾患で15.3%、3位は脳血管疾患で8.2%、4位は老衰で7.6%、5位は肺炎で7.2%、6位は不慮の事故で3.0%、7位は誤嚥性肺炎で2.7%、8位は腎不全で1.9%、9位は自殺で1.5%、10位は血管性等の認知症で1.5%である [3] [4] [5] 。 世界保健機関 (WHO) の2016年度の統計では、人口10万人中の日本の自殺率と世界ランキングの高い順のランキングは、男女合計は18.5人で14位、男性は26.0人で17位、女性は11.4人で8位である [6] [7] 。
自殺した著名人一覧 本節の一覧には明治から現在までの人物を収載する。江戸時代以前の人物については「#近代以前」を参照。 その自殺について強い疑義のある者に関しては「#その自殺に強い疑義のある者」を参照。 著名活動を行っていない人物(特筆性のない人物)については掲載しない。
- 「死」の定義及び判定に関する諸問題
- 統計と原因
- 生物学的な死の説明
- 臨死体験
- 死のステレオタイプな表現
- 参考文献
- 外部リンク
どのような状態になったことを「死」とするのかという事については、各地域の文化的伝統、個人の心情、医療、法制度、倫理的観点などが相互に対立しており、複雑な様相を呈している。例えば、医学的な見解の一つに着目してみた場合でも、そこには様々な見解がありうる。養老孟司は次のように指摘した。
世界においては1日あたり、おおよそ15万人が死を迎えるが、そのうち2/3は高齢による加齢関連が死因である。先進国になるとその割合は高く、90%ほどが加齢関連である。また日本では、およそ23秒に1人が死亡しており、悪性新生物(腫瘍)が死因の最多を占める。 人が死に至る原因を死因と言う。 直接的に死亡に繋がった原因の事を「直接死因(direct cause of death)」と言い、直接死因を招いた原因を「原死因(underlying cause of death)」と言う。[要出典] (一般的な死因の分類と必ずしも一致するわけではないが参考までに)死亡診断書での「死因」の分類では次のようになっている。 1. 「病死および自然死」 2. 「不慮の外因死」(Accident) 2.1. 「交通事...
死に至った場合、生物体は次第に崩壊に至る。これは主として二つの作用による。 一つは、生物体自身が自らを分解することである。たとえば消化酵素のように、生物体を分解することが可能な酵素は生物体内のあちこちに存在しており、これによって生物体が分解されないのは、生命活動のひとつとして、それらを隔離した状態にする活動があるからである。死によってそれが止まれば、生物体は自ら分解を始める。 もう一つは、他の生物に分解されることである。生物の体は、それ以外のさまざまな生物にとって有益な栄養源である。特に微生物は常に空気中や地面などから侵入を試みている。これが成功しないのは、生きた生物には免疫の働きがあるからである。死によってその活動が止まれば、たちまちそれらの侵入と繁殖が始まる。
仮死状態から医学処置などで蘇生した人の4 - 18%が仮死体験の状態で体験した出来事を報告する。つまり、医師などによって死亡したと判定されたのに、時間を経て再び生き返る人がいる。別の言い方をするなら、仮死状態から生き返る人である。ゆえに「臨死体験」と呼ばれている。 有史以来、「臨死体験」をした人々が多くいたようであり、西洋でも東洋でも類似の内容が様々な文献に記録されているという。ハーバードで宗教学の講義を担当するキャロル・ザレスキーは、中世の文献は臨死体験の記述であふれていると指摘した。また、日本でも『今昔物語』『宇治拾遺物語』『扶桑物語』『日本往生極楽記』などに臨死体験そっくりの記述があるという。 近年では医学技術により、停止した心臓の拍動や呼吸をふたたび開始させることも可能になったため、...
比喩的な用法
自然言語はその成り立ちからして基本的にメタファーで出来ているものであり、死という表現も、何かしら生命に擬せられる存在が、その比喩的な「命」を失うような場合にも使われる。「ローマ帝国の死」、「星の死」などである。 現在[いつ?]では、機械装置などが破損した場合に「死んだ」などと形容されることもある。とくにコンピュータに対しては、電源が切れた、クラッシュした、あるいはプロセスが停止したなどの状態を比喩的に「死んだ」と表現することがあり、その延長で「プロセスを殺す」(進行中の処理を停止させる)などといった比喩表現も使われる(一例を挙げれば、UNIX系オペレーティングシステムでは単なる比喩に止まらずプロセス停止コマンドとして'kill'コマンドが存在している)。生命の不可逆的な死とは異なり、これら機械の比喩的な死では破損した部品を交換するなり修理して、コンピュータの場合はクラッシュしたプログラムに関するメモリを破棄して記憶媒体から読み出しなおすなど復旧させる方法は幾らでもある。特に技術筋にもなると「異常や故障が手に負えなくなり、それを破棄して異常のないものに入れ替えする以外に対処方法がな...
兵士が死ぬときの表現
英語やフランス語では、兵士が敗北を喫したときに「ほこり(土)を噛む(英語:bite the dust、フランス語:mordre la poussière)」、ドイツ語では、「草を噛む(Ins Gras beißen(ドイツ語版))」という表現が使われる。土を噛むという表現は、古代ギリシアのイーリアス(2, 418)などにも見ることができる。 日本語では、砂を噛むは感情が湧かないような時の表現で、意味合いは異なる。コンピュータゲームでは、敗北を喫するときに使う表現として「床ペロ」という言葉が使われる。
芸術作品の死
芸術作品が、人の目に触れぬようになったり(死蔵)、作者の意図した事柄が部分的にすら受け取られなくなった場合、その作品は意味をなくし" 死ぬ "とされる。 古代ギリシャ、古代ローマにおいて人間は死すべきものと呼ばれ、神々、則ち不死なるものの永遠性との対比によって、時間的に限られたものとイメージされ、芸術家や詩人とは、この限界を乗り越え人間と神々を媒介するものと考えられた[要出典]。現在[いつ?]でも芸術作品は "不死性" と結び付けられて捉えられることが多い。 ヴァルター・ベンヤミン(1892年 - 1940年)はすでに"死んでしまった"芸術作品の「救済」が歴史家の使命であると考えた。 20世紀後半には、クンデラや大江健三郎らが、「小説の死」、「文学の死」といった言葉を用いた。 1. 実は死んでいない - シャーロック・ホームズのライヘンバッハの滝での死闘後からの復活。「ギャグキャラじゃなければ死んでいた」など、人気キャラクターを作者やファンが殺せなくなったり、作風として生きている、もしくは作品を盛り上げるために一時的に死んだように装われるプロット・デバイス。
養老孟司『死の壁』新潮社、2004年。ISBN 978-4106100611。エリザベス・キューブラー=ロス『死ぬ瞬間 - 死とその過程について』中央公論新社、2001年。ISBN 4-12-203766-2。Death (英語) - スタンフォード哲学百科事典「死」の項目。『死』 - コトバンク杏林大病院割りばし死事件 (きょうりんだいびょういんわりばししじけん)とは、 1999年 ( 平成 11年) 7月10日 ( 土曜日 )に 東京都 杉並区 で 綿菓子 を食べていた男児が転倒して、 喉 を 割り箸 で深く突き刺し、その後死亡した事故 [1] 。 単に 割り箸事件 とも呼ばれる [2] 。 その後、 刑事 ・ 民事訴訟 で医師の過失の有無が争われたが、いずれも医師に過失はなく男児の救命は不可能であったとの判決が下った [3] [4] 。 経緯. 事故発生. 1999年 ( 平成 11年) 7月10日 (土曜日)、男児が兄と一緒に教員である母親に連れられて、東京都杉並区で行われた 盆踊り 大会に遊びに来ていた。
ここでは、高い推定値による死者数が10万人以上となる全ての戦争について一覧を載せる。これには軍人と民間人の両方の死者数が含まれる。直接、戦争によって死亡しただけでなく、それによって引き起こされた戦闘、病気、飢餓、虐殺、自殺、ジェノサイドによる死者も含む。
紅麹サプリ事件 (べにこうじサプリじけん)は、 2024年 ( 令和 6年) 3月22日 に発覚した、 日本 の 製薬会社 である 小林製薬 の製造した 紅麹 を 原料 とする サプリメント が原因と疑われる死者5名を含む健康被害を多数出した事件である。 概要. 悪玉 コレステロール を下げる効果をうたった [1] 「 紅麹コレステヘルプ 」など、 機能性表示食品 として国に届け出た3商品を摂取した 消費者 ら5人が死亡、 入院 者数は240人以上、相談件数延べ94,000件(4月18日現在)となった [2] 。 有毒 ・ 有害 な 物質 が含まれている疑いがあるとして 食品衛生法 に基づき回収が命じられた [3] [4] 。
死因というのは、人の年齢帯によって大きく異なっている。 また先進国か途上国であるかによっても大きく異なっている。 先進国と途上国. 日本. 「 日本の健康#日本の死因 」も参照. 日本でも年齢帯によって死因の分布は大きく異なっている。 全年齢帯を混ぜた統計. 全ての年齢帯をごちゃまぜにした統計を説明すると、2017年(平成29年)の日本での死因順位は、1位が 悪性新生物 で27.8%、2位が 心疾患 (高血圧性を除く)で15.2%、3位が 脳血管疾患 で8.2%、4位が 老衰 で7.6%、5位が 肺炎 で7.2%、6位が不慮の事故で3.0%、7位が 誤嚥性肺炎 で2.7%、8位が 腎不全 で1.9%であった [2] 。